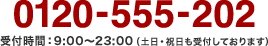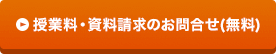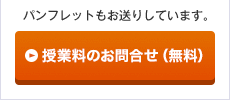2011年12月
2011年12月29日
愛知県 「今年注目の時事関連問題④」
入試で細部まで問われることは少ないですが、浅く広く概要を理解しておく必要があります。
野田氏は第59代首相に就任し、9月に野田内閣が発足しました。
・福島第一原発事故の早期収束と放射能被害防止
・円高対策
臨時増税を示唆しています。
内閣の基本方針をきちんと理解し、自分の言葉で説明でき、自分の意見を述べられるようにしておくことは大切です。
2011年12月27日
愛知県 「今年注目の時事関連問題③」
2011年12月24日
愛知県 「今年注目の時事関連問題②」
2011年12月23日
愛知県 センター試験直前の対策・学習法
こんにちは。家庭教師トライの愛知県本部です。
センター試験まで残り22日となりました(12月23日起算)。
特に23日からはほとんどの高校は冬期休暇に入ります。
環境が整い、学習時間も増し、一気に得点を伸ばす大きな期間です。
さてセンター試験の対策と言えば沢山のことが世の中には出回っています。
今回はトライ式学習法の中からいくつかご紹介致します。
①制限時間の75%の時間で解く訓練をすること
50分の試験問題を50分ギリギリで解けるように訓練しても本番は時間が足りなくなることがあります。
基本問題については、最終的には75%程度の時間内で解けるように訓練をしていきます。
これにより、ケアレスミスや、 無駄な思考をなくしていく訓練にもつながり、確実な得点力につながっていきます。
②問題解答の時間短縮には書写をすること
字が汚い子は当然、字を綺麗に書くように訓練をします。
しかし、字が綺麗な子であっても書くのが遅い子がいます。
字が綺麗だからといって遅いことを気にも留めない方がいらっしゃますが、大きな間違いです。
字を書く時間も立派な試験時間の一部。書写を毎日、時間制限をもって取り組む訓練をする必要があります。
毎日、取り組むことで驚くほど綺麗に早く書けるようになるのです。
③本番と同じ曜日、同じ時間に学校へ行ってみること
本番のシミュレーションは常に平静を保つためには必要なことです。
途中、思いもかけないハプニング(バスの渋滞など)に合うとも限りません。
事前に行ってみる事によって、その全ての状況を把握することが出来ます。
ラッシュでもみくちゃにされ、 駅で降りれなかった子も何人か現実にいらっしゃいます。
その他にも沢山のポイントが「入試合格虎の巻」には載っています。ぜひ皆さんに活用して頂きたいと思います。
ご興味があるかたは「0120-555-202」までお問い合わせください。
事前に立てた「合格のための必要得点率」を改めて確認し、
必要な学習を必要なだけ効果的に行い、志望校合格を達成しましょう。
2011年12月19日
愛知県 冬休みの勉強法(高校生)
2011年12月18日
愛知県 冬休みの勉強法(中学3年生)
3者面談も終わり、受験まで秒読み段階になってきました。
冬休みは受験に向けての対策をじっくりと練れる最後のチャンスです。
自分の苦手分野を潰して本番に臨みましょう。
特に英語については、長文が必ず出ます。
この冬休みを使って長文に慣れておきましょう。
愛知県の公立高校入試問題はそこまで難解な問題が出るわけではありません。
400字程度の英文に慣れておけば問題ないでしょう。
まずは教科書レベルの英文をしっかりと理解できるように、自分で翻訳してみましょう。
長文については単語、熟語、文法についての基礎がしっかりとできていれば対応できます。
今までの学習において漏れがないかをしっかりとチェックしておく必要があります。
一文一文を読めても全体を理解できないといけません。
長文を読み解くコツは全体の流れを把握できるかどうかです。
この冬休みになるべく沢山の長文に触れておきましょう。
トライ推薦の問題集などを使って効率よく勉強していきましょう。
2011年12月14日
愛知県 【大学受験シリーズ⑧】センター試験対策 倫理・政治経済
2011年12月12日
愛知県 【大学受験シリーズ⑦】センター試験対策 現代社会・地理
日本史・世界史に続き、今回はセンター試験 現代社会・地理編をお送りします。
≪センター試験:現代社会≫
■試験時間
60分
■配点
100点
■前年度問題構成
大問6題・小問36問(全問必答)
①現代社会の諸問題…22点
②国際社会の安全保障…14点
③日本の地域社会の諸問題…22点
④青年期の対人関係…14点
⑤日本の株式…14点
⑥地方自治…14点
■傾向と対策
◇正誤文選択問題が中心
昨年は設問36問中22問が正誤文を選ぶ選択問題でした。
統計資料読み取り問題・時事問題・課題追究の出題は頻出です。
◇基本をしっかり
問題の内容は教科書レベルの標準~やや難になっています。
ここ数年、公民3科目の中で平均点が一番低い科目です。教科書と合わせて資料集も見ておくとよいでしょう。
◇勉強は各分野バランスよく!
試験は各分野から満遍なく出題されています。
倫理分野…青年期・地球環境問題・資源エネルギー・少子高齢化
政治分野…日本国憲法・基本的人権・地方自治
経済分野…金融・財政制度・日本経済の変遷・雇用労働問題
以上が頻出単元ですので、対策必須です。
◇まとめ
各分野の頻出単元、統計資料読み取り、時事問題、課題追究問題の練習をしっかり行いましょう。
≪センター試験:地理≫
■試験時間
60分
■配点
100点
■前年度問題構成
大問4題 小問36問(全問必答)
①自然環境と地域…16点
②世界の資源・産業…18点
③生活文化と都市…17点
④アフリカの自然と生活…18点
⑤現代社会の諸問題…15点
⑥地域調査…16点
■傾向と対策
◇図表利用問題が7割を占める
地図・グラフ・統計表・写真からの出題が7割以上を占めます。
組み合わせ問題(図・統計表などと、文章・語句の組み合わせを問う問題)も頻出です。
◇基本を幅広く
センター試験では、細かな地名や地理用語を問われることは少なく、教科書レベルの内容がほとんどです。
全体的にまんべんなく出題されています。
地図帳で都市の位置を確認すること、時事問題のチェック、地形図の読図を必ず練習しておきましょう!
◇勉強のポイント
・各分野の基礎知識を押さえる…時事問題も忘れずに押さえることがポイントです。
・分野のヨコのつながりを押さえる…各分野を別々に学習していきますが、ヨコ関係が問う出題が多いです。
・地形図に慣れる…新旧の地形図の変化を問われる問題が出ています。
昨年度は6枚の地形図が出ていますので、練習が必要です。
センター試験まで日程が迫ってきております。体調管理に気をつけて頑張ってください!
2011年12月11日
愛知県 冬休みの勉強法(中学1・2年生)
期末テストが終わり、三者面談の真っ最中という方も多いのではないでしょうか。
中学1・2年生の皆様にとっては、「入試はまだまだ先のこと」と考えている方もいらっしゃると思います。
しかし、入試の過去問を見てみると、実は今習っていることがそのまま入試に出題されているのです。
≪数学≫を例に取り上げてみましょう。
愛知県の公立高校入試は、AグループとBグループの2回試験があります。
Aグループの問題の60%、Bグループの問題の45%は、中学1・2年の学習内容のみで解ける問題です(2011年入試)。
そして、中学1・2年生の2学期で習う単元の中でも、特に重要なのは以下の単元です。
●中学1年生
①方程式の利用(9月)
2年生の二次方程式に繋がる単元です。
計算力の他に、文章を読んで情報を整理し、整理した情報をもとに式を組み立てる力が必要です。
●中学2年生
①一次関数の利用(9月)
速さのグラフ・水かさのグラフや、グラフと図形を組み合わせた問題など複雑なものです。
いくつかパターンがあるので、1つ1つを整理して理解しましょう。
②図形の証明(10~11月)
図形の証明は、まず合同条件を覚えてしまうことがポイントです。
次に条件に合うポイントを文章と図形から探し、解答パターンに沿って文章を並べるだけです。
まずは2学期に行われたテストの見直しをすることで、できているところ・できていないところを整理してみましょう。
整理がうまくできない方・弱点はわかったけれども克服の方法に悩んでいる方は、是非トライへご相談ください。
冬期講習受付中です!
2011年12月8日
愛知県 【大学受験シリーズ⑥】センター試験対策 日本史・世界史
物理・化学に続き、今回はセンター試験 日本史・世界史編をお送りします。
≪センター試験:日本史B≫
■試験時間
60分
■配点
100点
■問題構成
大問6題(全問必答)
①テーマ史…12点
②原始・古代史…18点
③中世史…18点
④近世史…17点
⑤近代史…12点
⑥近現代史…23点
■傾向と対策
◇正誤文選択問題が中心
昨年は設問36問中22問が正誤文を選ぶ選択問題です。
正誤の組み合わせを選ぶ問題も複数出題されるので、選択肢を吟味し、正しく正解を導きだす力が必要です。
年表の中で人物名や、出来事が起こった場所などをきちんと確認しておきましょう。
◇基本をしっかり
問題の内容は教科書レベルの基本的・標準的なものから出されています。
また史料をみて答える問題も例年出題されているので、教科書と合わせて図説も見ておくとよいです。
◇近・現代史が高得点のカギ
試験は全時代から満遍なく出題されていますが、その中でも近・現代史の出題割合は4割あります。
その他の時代の割合が2割前後であるので、近・現代史の得点率を伸ばすことが日本史高得点のカギになります。
政治・外交史を内閣ごとに整理して覚えましょう。
◇テーマ史は少しさかのぼった過去問で対策
連続して同じテーマからの出題はされていないので、少しさかのぼった過去問やマーク模試で対策を行いましょう。
近年の出題テーマは以下の通りです。
23年:明かりとエネルギーの歴史
22年:武士の歴史
21年:地方行政区画の歴史的変遷
≪センター試験:世界史B≫
■試験時間
60分
■配点
100点
■問題構成
大問4題 小問36問(全問必答)
■傾向と対策
◇出題形式は正誤文選択問題が7割
出題形式は正誤を判定する問題が全体の7割を占めています。
正誤の組み合わせを選ぶ問題も複数出題されるので、選択肢を吟味し、正しく正解を導きだす力が必要です。
◇基本を幅広く
出題範囲は、時代や地域によって偏りは少なく、幅広く知識をつけておく必要があります。
難易度としては、教科書レベルのものが多いので教科書の内容をしっかりと押さえましょう。
地図や資料からの出題もあるので、図説も合わせて確認しましょう。
また、正誤問題では複数の知識を総合して判断するものもあるため、
用語をただ丸暗記するだけではなく、知識をつなげて理解することが必要です。
◇中国史・ヨーロッパ史は頻出
幅広い内容から出題されているが、中国史やヨーロッパ史の問題は頻出です。
古代から現代までを大きな流れのなかで押さえておきましょう。
中国史では、特定の時代だけでなく税制の変化や官吏任用制度の変遷等、時代をまたいでの出題も多いです。
ヨーロッパ史では、中世の封建制度の崩壊や産業革命等の時代の流れを大きく変化させた出来事がよく聞かれます。
◇タテとヨコのつながり
各国や地域ごとにどのように歴史が変化しているかを捉えるだけではなく、
同じ時期に別の国ではどのような変化があったのかということを繋げて整理しておくことが大切です。
国々がどのように関わって来たのかを意識して学習を進めましょう。
◇文化史・社会・経済史で高得点を狙う
歴史の勉強というと政治史に偏りがちですが、高得点を狙うのであれば、文化史・社会・経済史もしっかり捉えましょう。
芸術の思潮は、経済や社会の動きと関連させて覚えましょう。
≪歴史学習のコツ≫
★まずは教科書内容の理解をしましょう!
★センターの過去問で演習をし、解説を読む中で知識の増加を図りましょう!
★参考書は何冊も持たず、使いやすいものを繰り返し使いましょう!
★自分で年表やメモリーツリーを作り、覚えやすい工夫をしましょう!