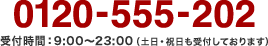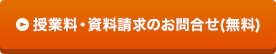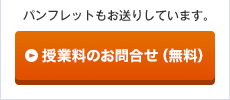2011年3月
2011年3月25日
テストに強くなる!④
テスト対策の第4弾です!
前回は、ノートのまとめ方や使い方をあげました。
今回は、先輩方が実践している点数アップ法をご紹介します。
①毎日の音読。英語の教科書・国語の教科書を毎日欠かさず、5~8分でもよいので音読する。
②テストの間違った問題ではなく、たまたま正解した問題をノートに3回、やり直しをする。
③ケアレスミスをした問題をピックアップして、類似問題を繰り返し解く。間違えた問題を集めた、間違いノートを作る。
④朝起きてからの短時間学習の習慣をつける。
先輩達も同じように苦しんで、対策を練ってきました。
一人ひとりにそれぞれあった対策の方法があると思います。
先輩の方法を試してみて、自分にあう学習法を見つけてみてください。
2011年3月17日
テストに強くなる!③
今回も テストに強くなる方法を伝授します。
私は、担当教師に、生徒の普段のノートを見てくださいと伝えます。
なぜでしょう?
自学自習の基本中の基本は、何度も復習したくなるノート作りにあると考えています。
授業中に先生が黒板に書いた文字だけでなく、雑談の内容なども吹き出しにして記入しておくと、ノートを開いた瞬間に、その授業のあらゆる情報が目に飛び込んできます。
こうしておけば、
ノートを見返すだけで、試験準備は万全です!
また、授業中に「 なんでだろう? 」と疑問に思ったことは 質問枠 を作ってそこに記入しよう。
そうすれば、質問したかった内容を忘れることなく、後から家庭教師の先生や友達に聞くことができます。
自分が何を考えて、どこで解らなくなり、何を質問したのかが いつ振り返っても理解できます。
また、色分けしたマークやシールを使って重要項目を見返す。
さらに、内容を図式化することで更にハイレベルなノートになります。
ノート作りが楽いと、テストにもっと強くなります!
ぜひ試してみてください。
2011年3月14日
テストに強くなる②
この度の地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
よく、担当の生徒さんに 「教師の癖を見つけてごらん」 とアドバイスしています。
授業を聞いて全てノートに書き写すことも大事ですが、先生が伝えようとしている内容をいかに読み取るかが重要です!
テストは、先生が話した内容を生徒がどれだけ理解して受け止めているかを測る物差しでもあります。
今回は、授業を楽しみながら テストで点数を獲得できる方法 をご紹介します。
それは、「教師の癖を見つけて」テストに出るポイントを効率良く把握する方法です。
先生が「ここ大事だぞ!」と言ったところはもちろん大事ですよね。
更に、「教科書のココとココに載っている」…などといった教科書指摘ポイントも大事です。
授業で先生が強調したポイントや声のトーンに変化を感じたら チャンスです!
まさに、先生が注意を引くために行った テストに出すぞ ポイントです。
テスト前には、ノートに記入したテストに出すぞポイントを見直してください。
簡単な方法ではありますが、楽しみながら対策が出来、点数につながります。
テストに強くなる方法はいくらでもあります。
是非、トライの教育プランナーにご質問ください。
では、また次回。
2011年3月9日
テストに強くなる!①
コツコツやる家庭学習が苦手・・・でも試験では良い点数を取りたい!
そんな生徒さんに試験直前の対策が楽になる「授業の聞きどころ」、「出題のヒント」を教えます。
色チョークで書いたところはやはり試験によく出ます。
当たり前のようですが、色チョークで書かれたところから多く出題される傾向にあります。
社会科を例に挙げて説明しましょう。
社会などのテスト対策は、基本的には暗記です。出題される内容は、教科書で太字になっているようなキーワード、時代の転換点やトレンドを象徴するような出来事や人名などが多いです。
板書の中で色付きチョークで書くような事項は、ここは重要部分だと強調しているわけで、当然テストにもよく出されます。
しかし・・・!暗記は暗記でもただ覚えればいいというわけではありません。
たとえば地理のキーワードで、「西岸海洋性気候」というものがありますが、これは「偏西風」や「北大西洋海流」などの用語と関連付けて覚えなければ意味がありません。ヨーロッパの大西洋岸はなぜ高緯度のわりに温暖なのか、その結果どんな産品が産まれ、人々がどんな生活を送っているのか。これらを筋道立てて理解せずに、単語だけ丸暗記しようとしても、覚えにくく、結果何の事か分からないといったことは良くあります。
試験では単なる丸暗記で埋められるような問題ではなく、これらのキーワードを関連付けて出題されることが多いのです。日頃からキーワード間の関連性を意識して覚えるようにしていきましょう。
2011年3月7日
高校数学 点数の取り方 4つのポイント
①数学の楽しさを知る
数学の面白さは、解くまでの道筋が論理的で、曖昧さがないことです。
誰が見ても正しい事は正しく、間違っていることは間違っています。
ただし初めから苦手意識を持っていると、数学をおもしろいとは感じません。
新高1生は、高校入学をきっかけに、新鮮な気持ちで数学に取り組んで欲しいと思います。
「考えることは楽しい」。よって、数学は楽しい。
②必ず予習・復習をしよう
高校の数学は計算も重要ですが、『なぜそうなるのか』という論理を説明できないと本当に理解したとは言えません。
日々の授業で「わかった」と感じるためには、その前後に論理をじっくり考えるための時間が必要です。
家庭学習で予習をやった上で授業に臨むと、授業の内容がわかりやすくなります。
授業には「復習」をするつもりで臨むのがいいでしょう。
さらに、授業で理解できなかったところを友人や先生に質問して理解するようにしたり、
もう一度自分で考えてみて理解しているかどうかを確認したりすると効果が高いです。
きちんと復習することで、次の授業内容の理解に繋がっていきます。
③ 必ず自分で解こう
数学の勉強では、答えを眺めて解ったつもりになっていても、実際に問題を自力で解こうとすると解けないことがあります。
いちいち計算するよりも、解答を眺めて理解していく作業の方が楽ですし、とりあえず勉強した気分にはなります。
ただ、それだけでは数学の力を本当に伸ばしていくことは難しいでしょう。
必ずノートにきちんと計算式を書いたり図を描いたりしながら解いていくこと。
そうすることで、自分自身が本当に理解できているかどうかを確認することができます。
④わからない問題でもあきらめない
わからない問題にぶつかったとき、簡単にあきらめてはいけません!
解けない問題を解こうとする過程(プロセス)が大切であり、それが本当の力を伸ばす源となります。
難しい問題が自力で解けたときは本当に嬉しいものです。その喜びがまた、次の問題を解こうとする力に繋がります。
どうしてもわからない問題があったら、遠慮せずに質問すること。
解らない問題を、絶対にそのままにしておかないことが大切です。
さあ、みんなで『 学ぶ楽しさ 』を経験しましょう!