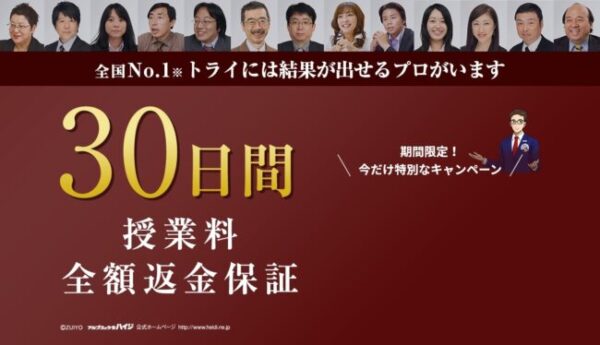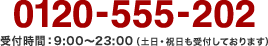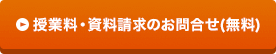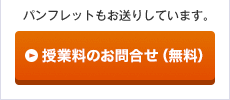2022年6月24日
佐賀県 7月と言えば・・・?
こんにちは!
家庭教師のトライ佐賀校のブログ担当です!
今日のテーマ
◇◇◇◇ 7月の代名詞 ◇◇◇◇
もうすぐ7月がやってきます。
7月といえば何を思い浮かべますか?
「うーん・・・。なんだろう・・・。」と、いまいち特徴のない月だと思います。
今日は、そんな7月についてお話していこうと思います!
7月:文月(ふみづき)
7月は、旧暦で「文月」とよばれていました。
この「文月」という呼び方、7月のある行事に基づいてつけられた呼び方なんです。
7月の行事といえば、ズバリ 「七夕」です。
七夕には、短冊に願い事を書きますよね?
実は、この行為が由来になっています。
文(ふみ)をしたためて願う月だから文月。
他には稲穂がふくらんでなかにお米が含まれるようになる「含み月(ふくみづき)」 という説もあります。
七夕について
はた織りが上手な神様の娘『おり姫』と働き者の牛飼いである『ひこ星』は、神様の引き合わせで結婚し仲良く過ごしていましたが、楽しさのあまり仕事をせずに遊んでばかり。
激怒した神様は天の川の両端に引き離してしまいましたが、悲しさのあまり元気をなくした2人を見かね、7月7日を年に1度だけ会える日として許しました。
夏の夜、8時ごろに東の空を見上げると、3つの明るい星が見られます。
それらの星を線で結ぶと大きな三角形ができます。これを「夏の大三角」と言います。
ベガは織りひめ、アルタイルはひこ星にあたります。
これらの星は7月7日ごろにいちばんよく見えることから、七夕の言い伝えが始まりました。
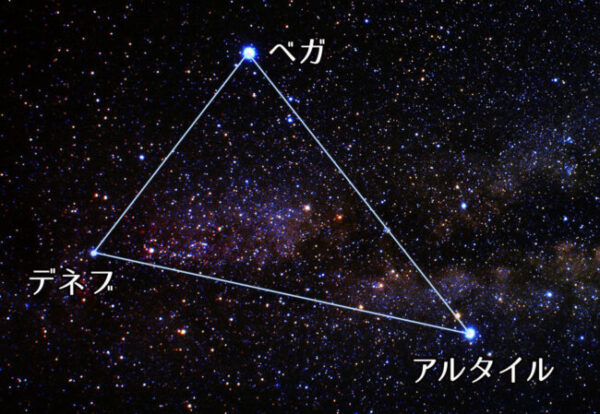
人々は「織りひめさまのように、はた織りやおさいほうが上手になりますように」「織りひめさまのように願い事が叶いますように」と、野菜やくだものをそなえて、おまつりをするようになりました。
やがて、いつしか人々は「上手に字が書けますように」「織りひめさまのように願い事が叶いますように」と、笹や竹に五つの色のたんざくをかざるようになりました。
いかがだったでしょうか。
現在トライでは、楽しく学べる環境を整えています。
興味のある方はぜひ以下の画像からホームページに飛んで詳細をご確認ください。