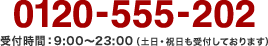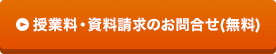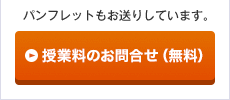2011年9月
2011年9月28日
栃木県高校入試 国語①漢字・語句・文法の傾向と対策
2011年9月27日
栃木県高校入試 社会④公民(経済)の傾向と対策
栃木県高校入試の傾向と対策、今回は公民の経済分野についてご紹介します。
◆経済の傾向
大問8番が公民の総合問題になり、経済の問題が多く出題されています。
◆経済の対策
1.教科書に載っている太字を覚えましょう。
[経済の仕組み]
家庭・企業・政府のつながり、価格決定の基本、デフレーション・インフレーション・スタグフレーションの意味を覚えましょう。
[景気の変動と財政]
好況・不況の意味と[どういう過程で起こるのか]や、日本銀行の働き、税金の分類、企業の仕組みを覚えましょう。
2.新聞に目を通しましょう。
教科書に載っている言葉が、頻繁に出てきます。
新聞を読んで、わからない言葉があれば、図書館で調べたり、先生や両親に聞いたりしましょう。
経済は生活に直結していますから、受験に向けての勉強というよりは、
日頃の疑問を解決する機会と思って勉強すると、面白味も増すと思います。
◆社会の傾向と対策
栃木県では、歴史・地理・公民問わず、図や表を用いた問題が数多く出題されています。
教科書に載っている図や表は、非常に大事です。
図や表から、[何が読み取れるのか]をきちんと整理しておくことが、得点力に結びつきます。
宇都宮校
2011年9月26日
栃木県高校入試 社会③公民(政治)の傾向と対策
こんにちは。
今回は社会③公民(政治分野)の傾向と対策をお伝えしようと思います。
公民・政治問題は大問7で出題されます。
近年の出題傾向は以下の通りです。
H21年度出題問題 小選挙区比例代表並立制、参議院議員、団体交渉権
H22年度出題問題 空欄補充、国会、三審制
H23年度出題問題 ワイマール憲法、基本的人権、比例代表制
■傾向と対策
◆日本国憲法
→憲法改正(改正の流れを覚える)
三大原則(国民主義、平和主義、基本的人権の尊重)
三大義務(勤労の義務、納税の義務、普通教育を受けさせる義務)
非核三原則(持たず、つくらず、持ち込まず) など
POINT: 三大原則・義務をしっかり覚える。
◆基本的人権の尊重【三大原則の1つ】
→人間思想(ジョン・ロック、モンテスキュー、ルソー)
基本的人権について(公共の福祉に反しない限り認められる 等)
5つの権利(平等権、自由権、社会権、参政権、新しい人権)
POINT: ① 5つの権利の内容を把握する。
② 条文は用語をそのまま暗記する。
◆国会・内閣・裁判所の三権分立
→立法権・行政権・司法権のしくみ
国会について(衆議院・参議院のしくみ、国会の種類・仕事)
内閣について(内閣の仕事・しくみ、議院内閣制)
裁判所について(三審制のしくみ、裁判所の種類)
POINT: 国会・内閣・裁判所のそれぞれの仕事と各機関の役割をしっかり覚える。
◆地方自治
→地方自治のしくみ
住民参加(直接請求権、オンブズマン制度)
地方財政(地方分権、国庫支出金について)
POINT: 「1/50以上」などの数値をしっかり覚える。
◆社会福祉と国民生活の保護
→社会保障制度のしくみ(憲法25条、社会保障に対する対策 バリアフリーなど)
消費者として(PL法、クーリングオフ制度など)
労働者として(労働三法、労働組合、男女雇用機会均等法)
生活者として(3R、環境保護について)
POINT:高齢社会に伴って出題される頻度が高くなるのでしっかり単語を覚える。
公民(政治分野)で重要なポイントは
① 教科書の太字や学校で先生が黒板で赤や黄色で書いたところは押さえましょう。
② 各権利などのしくみ・内容・数値をしっかり覚えましょう。
過去の問題を見て分かるように、この問題が必ず出るとは言えず、政治全般をまんべんなく勉強することが大切です。
この問題なら解けるではなく、どの問題でも解けるようにしておきましょう。
次回は社会④経済をお伝えしたいと思います。
宇都宮校
2011年9月25日
栃木県高校入試 社会②地理の傾向と対策
2011年9月24日
栃木県高校入試 社会①歴史の傾向と対策
栃木県高校入試の傾向と対策、今回は社会の歴史分野についてご紹介します。
◆社会の試験の構成
1.3分野(歴史・地理・公民)基本問題 [8問]
2.3分野基本問題 [5問]
3.日本地理・地図 [5問]
4.世界地理 [5問]
5.日本の歴史(~江戸時代まで) [5問]
6.日本の歴史(明治以降) [5問]
7.公民(憲法・国会) [4問]
8.公民(経済・社会保障・国際) [6問]
※過去3年調べです。問題数は前後する可能性がありますが、
出題が例年通りの場合は、今年もこのような順番での出題が予想されます。
◆歴史の対策
教科書の単元でいうと、
文明の起こり~貴族社会/武家社会とアジア/世界の動きと天下統一/江戸時代とヨーロッパの近代化/近代日本の歩み/2つの世界大戦と日本/現代の世界と日本 からの出題です。
●大問5番
出題形式…選択式と記述式
傾向…毎年、あるテーマが与えられ、それに関する史跡などが箇条書きで示されます。
昨年は栃木県にまつわる史跡の問題、平成17年度は愛知万博に関する問題が出題されました。
対策…その年度の出来事に関係する問題が出題される傾向にあります。
日頃から新聞の一面に目を通し、ニュースで気になったことを図書館で調べるなどをしておくといいでしょう。
あるキーワードに対して、現代の出来事と歴史上の出来事をつなぎ合わせることが出来れば、
歴史が単なる暗記教科という認識もなくなり、歴史の勉強が面白くなります。
●大問6番
出題形式…選択式と記述式
傾向…歴史的な出来事が起きた時代背景と、同時期に起きた出来事などが出題されます。
たとえば、[日中戦争と太平洋戦争の間の期間に、日本で起きた出来事はどれですか]というような問題です。
対策…以前も紹介した[オリジナル年表]を作成することをお勧めします。
日本もしくは諸外国で歴史的な事件が起こった際の、各国の時代背景や文化を併せて覚えましょう。
横(時間軸)のつながりも大切ですが、縦(国ごと)のつながりも重要です。
宇都宮校
2011年9月23日
栃木県高校入試 英語④リスニングの傾向と対策
こんにちは。
今回は栃木県高校入試の英語④リスニングの傾向と対策をお伝えしたいと思います。
■傾向と対策
リスニングは配分が高く、100点中30点あります。15問×2点の配点です。
短い英文~少し長めの英文を聞いて、要旨を把握する問題が出題されます。
1、 疑問文の適切な返答問題
2、 親子・友達等の2人での対話から内容を把握して問いに答える問題
3、 少し長い英文を聞き、問いに答える問題
主にこの3つに分けられて出題されています。
記号で答える問題と記述で答える問題がありますが、きちんと内容を把握していれば答えに迷うことはないでしょう。
日常的な対話を聞いて内容を把握できるようになることが大切です。
日頃から英語を耳にすること・音読することから始め、英語の発音・対話を聞きとる力を身につけていきましょう。
リスニング対策の重要なポイントは
① 英語を聞くこと。
→洋楽、市販で販売しているリスニング対策用CD等を使い、英語を聞くことから始めましょう。
② 英語を話すこと。
→①で利用したものの英文を音読し、英語に慣れていきましょう。
音読することは英語全般に言えることです。
発音とスペルの違いを確認することができるので声に出していきましょう。
③ 「?」の後の問い・強調する部分に気をつけて聞くこと。
→「?」の後にはその答えがきます。つまり、答えに結び付くことが多いと考えられます。
注意して聞いてみましょう。
リスニングは聞くこと・話すことで変わってきます。
毎日、英語に触れることで変化が見られると思います。
例えば、通学時・下校時に聞くだけでも構いません。試してみてください。
次回は社会①歴史の傾向と対策をお伝えしたいと思います。
お楽しみに。
宇都宮校
2011年9月22日
栃木県高校入試 英語③英作文の傾向と対策
栃木県高校入試の傾向と対策、今回は 英語③英作文 の傾向と対策についてお伝えします。
英作文は苦手という人が多いのも事実ですが、対策は可能です。目をそむけずにチャレンジしてください。
平成22年度出題問題 英訳(部分・完全記述)2問、条件作文2問、テーマ作文1問
平成21年度出題問題 英訳(部分・完全記述)2問、条件作文2問、テーマ作文1問、整序結合(並替え文)1問
平成22年度出題問題 英訳(部分・完全記述)2問、条件作文2問、テーマ作文1問
平成23年度出題問題 英訳(部分・完全記述)2問、条件作文2問、テーマ作文1問、整序結合(並替え文)1問
<出題と傾向>
入試問題における大問[4]が英作文問題です。得点配分は
①「和文英訳」2点x2問=4点 ②「条件作文」3点x2問=6点 ③「テーマ作文」6点 の計16点。
<英作文のポイント>
・和文英訳
前後の文章の流れに沿った短文作成。文章を作成するというより慣用句を用いた解りやすい文での回答がベスト。生活の中で用いられる、ごくごく身近な文(言い回し)の回答が求められる為、教科書本文・例文等で覚えた文を思い返せれば問題ありません。
・条件作文
会話やメール文でのやり取り等に関する、口語型の条件作文。会話文特有の表現に対する文章理解と・答え方を覚えましょう。前後のやり取りから必要な内容を理解し、簡潔に回答できるよう、会話の読解等で学んだ表現方法で回答しましょう。
・テーマ作文
与えられたテーマに基づいて、「3文以上」(ピリオドが三つ以上ある文)の英文で回答する問題。例年、必ず[4]の③で出題されます。6点配分の英作文。自身の意見を問う問題なだけに、「I think~」(私は~と思う)を使った文章(これで1行作成で部分点ゲット)を作成できるようにし、残り2行で自身の意見を短くまとめられれば点数はしっかり得る事が出来ます。
・整序結合
並び替え文です。文全体の並び替えか、主語を除いた文の並び替えか、疑問文なのか等、問題文の把握をまず行い、適切な順で並べましょう。記号順で並び替える場合や、単語を抜き出して回答する場合があります。単語抜き出し型の場合は、文の頭の大文字小文字のミス、文末のピリオドや「?」等の記号の書きミスが無い様に注意しましょう。
<英作文まとめ>
全体の点数の中では16点と低めに配分されています。
問題を良く分析すると出題傾向は「お約束」の部類であり、かつ長文や複雑な文章をもとめる回答ではなく、基礎的な文章で回答できるので、しっかり日々の勉強を行っていれば身構えずに取り組む事が出来るのが栃木県の英作文の特徴といえます。
教科書等の基本的な表現を利用し、身近な内容を英語で答えられれば点数に結びつけることができます。英会話で第三者に説明する際にどう話すか等の表現を理解し、英会話が得意な人は積極的に問題を解いてみましょう。英作文として難しくとらえるよりも、前述の様に会話での繋がり、簡単な表現を基本通りに伝えられるかが問題のポイントです。
積極的に英語で表現しようとすれば、学校や生活の中で対策は身につきます。恐れずに英語に立ち向かって行きましょう。
2011年9月21日
栃木県高校入試 英語②対話文・長文読解の傾向と対策
栃木県高校入試の傾向と対策、今回は英語の会話文と長文についてご紹介します。
対話文の出題数 長文の出題数
平成21年度 4問 平成21年度 8問
平成22年度 4問 平成22年度 8問
平成23年度 4問 平成23年度 7問
≪対話文(大問3番)≫
◆傾向
登場人物は原則二人で、日本人と外国人の会話になっています。
内容は、日本と外国の習慣などの違いについて問われる問題が多いのが特徴です。
◆対策
①設問の下線が引いてある部分の前後に注意すること。
答えが隠されている可能性が大きいです。
②二人の対話において、結論は何を言いたいのかを考えながら読むこと。
対話文を読み、要旨文を完成させる問題が出題されることが多いので、この文は一体何を意図して作られた文章なのかを考えながら読むことが大切です。
≪長文問題(大問5番と6番)≫
◆傾向
大問5番は、物語文
大問6番は、説明文(理科分野や社会分野など)が出題されます。
◆対策
①段落ごとに数字を書きながら、文章を読むこと。
そうすることで、段落ごとの要旨がつかみやすく、文章の全体像が見えてきやすくなります。
②長文を読む前に、問題文に目を通すこと。
あらかじめ与えられている問題を頭に入れておくことで、どこに主眼を置いて読めばいいのかがわかります。
③多くの長文を読み、速読力、読解力をつけること。
初めは短めで簡単な文章から読み始め、徐々にレベルを上げていくことが大切です。
英語の文章に慣れることが出来れば、読解の過程で知らない単語や熟語が出てきたとしても、前後の文脈から意味を推測することができるようになります。
単語や熟語の意味を推測し判断する力は、高校受験のみならず、大学受験でも必須になります。
◎対話文・長文読解対策
求められていることは、「内容がきちんと理解できているか」です。
また、理解できたことを、英語で表現できるかを問う問題が近年多く出題されています。
宇都宮校
こんにちは。
栃木県高校入試の傾向と対策、今回は英語①単語・文法についてお伝えしたいと思います。
平成21年度出題問題 適語の選択・補充(6問)、語形変化(3問)
平成22年度出題問題 適語の選択・補充(6問)、語形変化(3問)
平成23年度出題問題 適語の選択・補充(5問)、語形変化(4問)
■傾向と対策
◆単語
対策:スペルミスがないよう書いて覚えることが重要です。
ローマ字読みで覚えてしまうとアクセントの問題で間違えてしまいます。
書く・読むを中心に単語だけを覚えるのではなく、動詞・形容詞等は熟語で覚えるようにしましょう。
◆適語の選択・補充
対策:Aさん、Bさんの会話文が出題されるので会話文特有の表現に対する答え方を覚えましょう。
例えば、「How are you?」→「I’m fine.Thank you.And you?」といったように会話文の答え方は
ある程度決まっているのでしっかり覚えていきましょう。
◆語形変化
対策:熟語で覚えることによって『to+原形』といったような問題をスムーズに解くことができます。
複数形にする時、単数のままでいい時などきちんと理解しておきましょう。
特殊な複数形『―es』『―is』になる動詞もしっかりチェックしておきましょう。
≪単語・文法で重要なポイント≫
①単語は書いて、読んで覚えること。
→決してローマ字読みで覚えないようにしましょう。
きちんとした発音で覚えることで今後の勉強の助けになります。
②熟語で覚えること。
→基本的に適語の選択や補充は熟語として出題されることが多いです。
③関連付けて覚えること。
→例えば、『見る』であったら『look,watch,view・・・』など多くあります。
1つの言葉に対していくつもの単語があるので、その時に一緒に覚えてしまうと後で覚える必要がなくなります。
次回は英語②会話文・長文の傾向と対策です。
お楽しみに。
宇都宮校
2011年9月20日
栃木県高校入試 理科④地学の傾向と対策
栃木県高校入試の傾向と対策、理科の最終回は「地学」こと、地球科学分野になります。
<地学に関して>
地学はⅡ分野範囲になります。
・大地の変化 (地層と過去の様子、火山と地震(噴火、火山岩と深成岩、地震の揺れと発生))
・天気とその変化 (気象観測、天気の変化(雲、霧、気圧配置、前線))
・地球と宇宙 (天体の動きと地球の自転・公転(天体の日周運動、星座)、太陽系と惑星(太陽、恒星、惑星))
※地学分野ではありませんが、今回は以下も解説します。
・自然と人間 自然と環境(微生物)、自然と人間(自然災害)
<出題と傾向>
例年大問2つと基礎小問で各単元から万遍なく出題されています。
地学はほかの分野と違って、規模の大きい内容の分野です。
しかし、実験や体験を実際にフィールドで行い、体で覚えることもできる分野です。
問題傾向は、
・ 実験観察問題 「日周運動・年周運動」「大気中の水の変化」
・ 思考問題 「大地の活動」「自然・環境・災害」
が基礎用語確認とともに出題されます。
「どうしてそうなるのか」、「どんな事によってどうなるのか」といった、理論・思考を問う論述問題が主体になります。
<地学のポイント>
「大地」と「大気」と「地球」
地学の分野は大きくこの3つに分けられます。それぞれ内容や系統がまったく違うため、さらにジャンル分けをして落とし込むことが可能です。かなり細分化できる為、単元単位での理解度の確認チェックは分類と共にしやすい分野です。
・「大地」に関して
地層、化石、火山に伴う火成岩に関しては、用語も多くしっかり回答できるようになりましょう。
また、火山活動や地震という、「災害」とつながっており、回答に応用思考を求められるのがこの分野。難敵ですが、ここでくじけずにしっかりと足元を固めていきましょう。
・「大気」に関して
注射器を使った「雲(水蒸気)」の実験。これを基礎にした気圧・水蒸気に関しての問題や、毎日天気予報などで見ている「天気図」に表される四季の気圧配置と気団、前線の天気と気温などがテスト問題として出てくる単元分野です。
・「地球」に関して
太陽の動きと季節に関して、星の年周運動・日周運動、そして惑星に関する出題分野です。
惑星問題以外は、栃木県なら空を見上げれば理解体感できる内容が多いはずです。
<地学まとめ>
一年生で「大地」を学び、二年生で「空(大気)」にはばたき、三年生で「宇宙(地球)」を目指す分野、それが「地学」です。
暗記項目として考えるとスタート時は量も多く、重いイメージが付きまといますが、そこを越えると、どんどん軽くなり、天まで届きます。
しっかり、足元を固め、大きく高く飛び立つイメージで勉強すれば、あっという間に最後のページまで進めるはずです。また、実験観察はそんなにパターンが多いものではありません。しっかり理解し、自分で説明できるようになれば「地学」は理科の点数の土台となってくれるはずです。
<自然と人間>
3.11。「自然と人間」、そして前出の「大地」にかかわる大問題が起きました。また、秋の台風でも西日本では大きな災害となった事は皆さんもご存じでしょう。この単元は座学ではなく「現実実習」です。学ぶべき内容やその答えは、皆さん自身がよく考えて探してみてください。