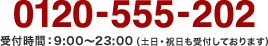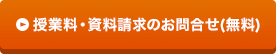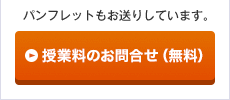2011年4月
2011年4月28日
山梨県 公立高校入試問題「英語」の傾向と小学生英語学習の必修化
こんにちは。家庭教師のトライ山梨本部です。
山梨県の公立高校入試問題を分析すると、「英語」には3つの特色が見えてきます。
① 冒頭のリスニング問題が全体の35%を占める
② 長文読解がメイン(文法、語彙の問題がほとんどない)
③ 英文作成問題が4問
【文法、語彙の問題がほとんどない = 理解が甘いと答えられない】
そして難易度はやや高めになっています。
リスニング問題では、30代から40代の世代が高校受験をした頃は、
英語を習い始めの中学生が聞き取りやすいスピード・内容でした。
今は、ご存知のように、ネイティヴが普通に会話をしているスピードを聞き取って答えるようになっています。
また、聞きとれたとしても、語彙力がないと意味がわからないような内容になっています。
配点ウェイトも高いので、十分な準備が必要です。
英語の難化傾向に拍車をかけるのが、「小学校英語の必修化」です。
小学校卒業までに単語数285語の学習が指定されました。
今の中学校一年生が、一年間で覚えるものよりも多い量です。
ということは、小学校で英語を学んだ生徒が高校入試を迎えるころには、
リスニングのレベルや問題のレベルがさらに引き上げられるでしょう。
しかし、不安感ばかりが先行すると、萎縮してしまい、かえって記憶や理解がうまくいかないケースがあります。
せっかく学ぶ機会ができたわけですから、それをチャンスと捉えて、しっかりと学んでいきましょう。
小学生や中学生は、自分で勉強を計画的に行うことや、つまづきを修正するのは、まだ難しい年齢です。
勉強は自分でやるものですが、上手にできるようになるまでは大人のケアが必要です。
せっかくの学ぶチャンスで、英語嫌いになってしまわないように、大人が上手にケアをしてあげたいですね。
2011年4月25日
多様化する山梨県立高校
こんにちは。家庭教師のトライ山梨本部です。
全国的に公立校の改革が進み、様々な新設学科、コースが設置されています。
山梨県の公立高校にも多種多様な学科、コースがありますが、
高校受験を迎える段階になってはじめて知る、という保護者の方や生徒さんに多く出会います。
大きな分類として、普通科、職業科、定時制にわかれているのは従来通りですが、
普通科でも例えば、理数科に重点を置いたカリキュラムで大学進学実績を高める理数科、
英語の時間数を増やし総合的な英語力を高める英語科、PCスキルを高める情報処理科など、
選択の幅が大きく広がっています。
「近くの高校」、「成績で入れそうな高校」という学校選びから、「目的別の高校選び」へと
頭を切り替えて高校受験を迎えるのが主流となっています。
*****************************************************************
【理数科のある主な高校】
甲府南高等学校
吉田高等学校
甲府東高等学校
巨摩高等学校
上野原高等学校
北杜高等学校
身延高等学校
【国際、英語科のある主な高校】
甲府第一高等学校(英語)
市川高等学校(英語)
白根高等学校(国際文理)
山梨高等学校(英語総合)
甲府商業高等学校(国際)
*****************************************************************
中3になると2回の校長会テスト(市町村によって実施時期が異なります)が行われ、
その結果によって受験校を絞り込むというのが山梨県の高校入試の特色です。
そのため、各高校とも倍率が極端に高くなることはありませんが、学力的には「接戦」となります。
確かな実力を身につけながら、校長会テストでも結果を出すこと、両方が大切です。
2011年4月22日
山梨県の新受験生のみなさん、入試まであと何日?
こんにちは。家庭教師のトライ山梨本部です。
先週のお話です。
浪人が決まり、来年の大学受験に向けて家庭教師のトライに入会された生徒さんが
「私、入試まで◆◆◆日しかないんです」と真剣な眼差しで話をしてくれました。
今の時期に、「入試まであと◆◆◆日」と数えている人はいますでしょうか?
この時期にカウントダウンをしている人は、ごく少数だと思います。
でも、私はこう思うのです。
あと何日で試験の日になるのかを考えたこの生徒さんは、
受験をするということをいち早く自分のことと受け止めてスタートできたのだと。
少し視点を変えて考えてみます。
「何日」と数えると3桁の数字になってしまい、少し漠然とした数になってしまいますから、
「あと◆◆週間」という考え方はいかがでしょうか。
週1回の授業であれば、何回授業を受けると入試になるというイメージができます。
例えば「大学入試センター試験」までを考えてみます。
来年のセンター試験は、1月14(土)15(日)の二日間に実施されると予測されます。
よって、今は4月の4週目ですから、あと「39週間でセンター試験」になります。
ということは、週1回ペースの授業を39回しか受けられないとわかります。
そうすると、過去問演習に10回使うならば、あと29回で全範囲を終わらせる必要があります。
29回で範囲が終わらせられるかどうか、その科目の単元数を知っておく必要がでてきます。
というように、いつまでに、どこまで勉強を進めておく必要があるのかという、
「自分なりの受験の設計図」を作ることができます。
もちろん、その通りに進むことはめったにありません。常に軌道修正をしていく必要があります。
ただし、行き当たりばったりで思いつきのように勉強をするよりははるかに目標に到達しやすいのです。
*********************************************************************
部活が忙しかったり、体育祭、運動会があったり、
山梨県の中学三年生は5月に修学旅行の学校が多いため事前学習があったり、
忙しい4月5月ですが、ゴールデンウィークのどこか1日でいいと思います。
カレンダーをみて、受験まであと何週間しかないのか数えてみてください。
そして、いつまでにどこまで勉強を進めておくとよいのかを頭をフル回転させて考えてみてください。
きっと何か「発見」があるはずです。
2011年4月19日
今、「地球儀」が売れているそうです。
こんにちは。
桜も葉桜にかわりはじめ、もうすぐゴールデンウィークを迎えます。
ゴールデンウィークが終わると、三期制(*)の中学校、高校では一学期の中間テストが始まります。
(*三期制:一年度が一学期 二学期 三学期に分かれています。 他に前期、後期の二期制をとる学校があります)
山梨県内の中学校の多くは5月に修学旅行がありますが、
修学旅行から帰って1週間から10日後に中間テストが行われる学校が多いようです。
テストまでの日程イメージを持っておかないと、十分対策を取れないまま、気づけばテストを迎えてしまいます。
三期制の中学校、高校の生徒さんは、
学校配られた「年間予定表」を見て中間テストの実施日を確認しておきましょう。
早い学校では5月12日前後からスタートします。
********************************************************************
先日ニュース番組で報じられていましたが、今「地球儀」が売れているそうです。
その原因は、学習指導要領の改訂にあります。
授業時間の増加がよくクローズアップされますが、学習内容も改訂されています。
国際理解に関する改善として、地球儀を授業で使用することが明記されました。
最近の地球儀には、テレビに接続して調べたい場所をタッチすると、
その場所の国名や説明がテレビ画面上に映し出されるものもあるそうです。
地球儀をカラカラと回しながら、いろいろな国を想像し、空想の旅に出る。
そんな経験を通して、みなさんが社会を好きになったり、興味を持つようになっていただければと思っています。
2011年4月14日
山梨 信玄公忌祭
こんにちは。
信玄公の命日とされます4月12日に、信玄公忌祭が甲州市の恵林寺にて行われました。
晴天に恵まれ、桜も咲き誇る中、きっと全国の歴史ファン、信玄公のファンが集まったようです。
山梨県の小学生、中学生が歴史に興味をもつきっかけになるとよいですね。
歴史に興味も持つ子というのは、身の回りになんらかの仕掛けがあります。
たとえば歴史マンガが揃えてあったり、保護者の方が歴史好きであったり、
歴史ふれるチャンスが少なからずあるようです。
歴史に限らず、天体に興味を持つ子は、星に関する本が家にあったりします。
どんな本を読ませようかと悩みは尽きませんが、読む読まないを考える前に、
さりげなく本棚にそろえておくのも一つの手です。
今は、図鑑も種類が豊富になり、またマンガで読みやすくした図鑑もあります。
動物に関するもの、植物に関するものでも、何か準備してみてください。
2011年4月10日
新年度の生活スタート
こんにちは。
甲府市のスポーツ公園の桜並木が満開です。
「日本さくらの名所100選」にも選ばれている富士川町の大法師公園も今が見ごろですね。
首都圏の大学では、入学式の中止や延期が相次いでいますが、
山梨大学の入学式は、6日に無事行われました。
********************************************************************
入学式、始業式も終わり、来週から本格的に学校生活が始まります。
そしてあっという間にゴールデンウィークがやってきます。
ゴールデンウィークに入るまでに一番大切なことは、
「一年間の生活パターンはこの時期に決まる」ということです。
新入生だけでなく、新二年生、新三年生も新年度からは環境が変わります。
たとえばクラス替えがあったり、部活では後輩ができたり、高校生ならば選択教科が加わったり。
「こうすればうまくいく!」という方法は人によってさまざまだと思いますが、
「こうするとうまくいかない…」というのはある程度パターンがあります。
「慣れるまで様子を見よう」
これは、要注意です。
「様子を見る」 = 「何もしない」 になってしまうケースが非常に目立ちます。
・慣れるまでは疲れているだろうから、学校から帰ってきたら「寝る」
→ 帰宅後寝る習慣が生活パターン化され、そのまま一年が経ってしまう。
・慣れるまでは疲れているだろうから、勉強は「難しくなってから」「点数が悪かったら」
→ 勉強をする時間がない過ごし方が生活パターン化されてしまう。
→ 結果が出てしまってから手を打つ方が大変。
授業は先に進むので、なかなか追いつけない。
生活パターンに組み込めていないので結局できない。
勉強に限らず、新しく物事を始めるとき、区切りのときというのは、
やり方を変える、生活リズムを変える絶好のチャンスです。
このタイミングをうまくつかんで、勉強を生活パターンの中に組み込んでしまうことをお勧めします。
また、去年は遅刻が多かった、という生徒さん。この時期に早めに家を出て遅刻をしない生活を送ってみましょう。
それが生活パターンになってきます。