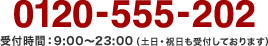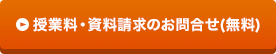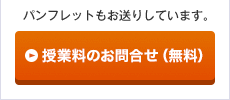2013年9月2日
千葉県 小学校低学年の宿題のやり方
こんにちは、トライ千葉校です。
新学期がはじまりまが、夏の宿題は終わりましたか?
夏休みが終わっても、これからも宿題は出続けます。
そこで、本日は、小学校低学年のお子さまの宿題の取り組み方について書いていきます。
ポイントは4つ。
1、宿題をする時間を固定する。
2、解き終わった後に、親御さんがチェック。
その時は、ノートの使い方、字の丁寧さ、範囲の宿題を全てやっているか、
間違えた問題から弱点を洗い出しているかを見る。
3、宿題と似た問題を別に出しているかどうか。
4、「宿題をやりなさい」と言っていないか。
1は、勉強のリズムをつくることが目的です。
低学年のときの習慣は、高学年以降に影響がでてきます。
例えば、夕飯前に宿題を終わらせる、朝早く起きて終わらせるなどです。
2は、宿題の完成度を高めるものです。せっかく時間をかけてやるわけですから、効果のあるものにしましょう。
そして、何よりも『空欄を埋めればいい』といった手を抜く姿勢をつくらないためです。
低学年のころに宿題を「やるだけ」の癖がつくと、これからも「やればいいや」といった感覚になってしまいます。
3は、宿題の定着率を高めるものです。
数問でもかまいません。似た問題を解くことで、できるできないがはっきりし、できたときには達成感を生み出します。
4は、親御さんの接し方です。あくまで本人に気付かせる発信をするということです。
例えば、「宿題をやりなさい」と強制するのではなく、
「今から何かすることがなかったかな?」「宿題はなんでするのかな?」「なんで丁寧にかくのかな?」
といった具合の声掛けが大切です。
そして、褒めてあげましょう!物を与えるのも最初のうちはいいかもしれません。
ただ、宿題は誰のためにやるのかを気付かせなければ、ずっと受け身になってしまいます。
家庭教師のトライ千葉校では、上記のことを、家庭教師がダイアログ学習法やウィークリープランで実現します。
低学年こそ一番の土台になる時期です。「まだ早い」ではなく、もう遅いかもしれません。
ご連絡お待ちしております。