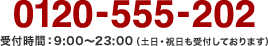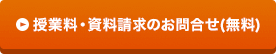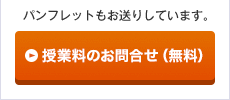2011年6月20日
島根県 センター試験対策【数学ⅡB】
数学ⅡBの平均点は例年50点程です。数学Ⅰの知識・理解が無ければ数Ⅱで得点することは難しくなります。現状、数ⅠAで60%の得点が出来ていない生徒さんは、まずは数Ⅰを完成させることを最優先に勉強を進めて下さい。
数ⅡBは大問4題の構成です。数Bの部分は選択科目になりますが、多くの受験者が数列・ベクトルを選択しますので、そちらの対策について述べたいと思います。
大問1 三角関数、指数対数関数
例年1問目には、三角関数が出題されています。あわてずにじっくり考えれば、解ける問題がほとんどです。基本的な事項を整理し、きちんと頭に入れておくことが得点獲得のカギになります。特に出題頻度の高い加法定理、2倍角・半角の公式は覚えておきましょう。
指数対数関数問題は、難易度の高い問題はあまり出題されていません。しかし、指数関数や対数関数の基本的な性質が頭に入っていないと解けません。また、他分野との融合問題の出題も予想されますので、基本的な事項をきちんとおさえておきましょう。
大問2 微分・積分
それほど難しい問題はないものの、全ての範囲がまんべんなく出題される傾向にあります。また融合問題として出題されているので、曖昧な知識では詰まってしまう可能性があります。関数の最大・最小、極大・極小、積分の計算などは繰り返して学習し、解答出来るようにしましょう。
大問3 数列
等比数列と等差数列と和の計算は、ほぼ毎年出題されております。群数列が出題されなくなり、代わりに階差数列が問われることが増えています。漸化式では、隣り合う2項間の関係を調べる問題がよく出題されます。
大問4 ベクトル
図形への応用は、ベクトルの係数比較(3点が一直線上にのる条件、直線の交点の位置ベクトルを求める、など)がほとんどです。基本計算、内積は頻出です。空間図形も、平面図形に帰着させて解く問題が出題されているので演習が必要になります。