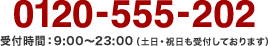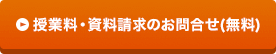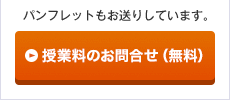2012年2月23日
福井県 中学校入学準備 ~数学でつまずかないために~
中学校入学準備シリーズ2回目は、数学でつまずかない為のポイントをお届したいと思います。
小学校では算数だった科目が、中学校へ上がると数学という科目になります。
教科の名前も変わりますし、今まで担任の先生が授業していたのが
科目別の教師に変わりますが、数を扱う学問であることに変わりはありません。
小学校の算数でやったことを土台とし、小学校で学んだ事が全て分かっている前提で
授業が進んでいきますから、小学校の算数で苦手が残っていると、
授業についていけず数学も苦手になってしまいます。
家庭教師のトライでも数学が苦手な中学生さんが多いのですが、
往々にして小学校で習ったことがまだきちんと理解できていない事が原因のようです。
たとえば、中学に入学してすぐの数学で扱う「正の数・負の数」は
6年生で学んだ小数・分数の混じった計算にさらに、+、-が関わった四則計算になります。
小数・分数につまづきがあると、正の数・負の数でもつまづいてしまいますし、
次の文字式の計算でもつまづいてしまいます。
簡単な足し引きは出来ても、分数が入ってくるとダメ、分数があるのを見るだけで
その問題を諦めてしまう、といった生徒さんもいらっしゃいます。
これは非常にもったいない事です。
また図形の分野でも、おうぎ形の面積や円の面積などの計算が苦手だと、
表面積や体積を求めるのが難しいですから、空間図形でもつまづいてしまいます。
特におうぎ型の面積は円錐の展開図で必ず出てきますから、しっかり計算できる必要があります。
中学校の応用問題で頻出の方程式の利用では、小学校で学んだ
道のり・速さ・距離の計算(みはじ)の計算を使うケースも多く見られます。
方程式が与えられれば解けるけど、方程式を自分で立てることができないという生徒さんが多いです。
こういったことを防ぐために、小学校の勉強は小学校のうちに理解しておくことが必要です。
今まで受けてきたテストや小教研を復習し、苦手な分野は今のうちに無くしておきましょう。