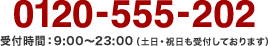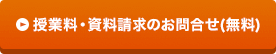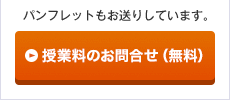2011年9月
2011年9月18日
福井県高校入試 理科③生物分野 傾向と対策
福井県立高校入試の傾向と対策。理科の第三回は生物についてお届けします。
福井県高校入試の理科・生物では、用語や文章記述などいろいろな出題形式が見られます。
傾向としては、細胞と生殖、生物のつながりが毎年のように出題されていますので、
しっかり押さえておきましょう。
生物に関しては、動物と植物のそれぞれ用語とその役割をきちんと理解しながら覚えることが大切です。
教科書の実験・観察・仕組・現象に関する写真・図をもう一度見直し、理解するようにつとめましょう。
2011年9月17日
福井県高校入試 理科②化学分野 傾向と対策
福井県高校入試の傾向と対策、今回は理科・化学についてです。
化学は、気体とその性質・状態変化・化学変化のきまり・化学変化とエネルギーがポイントです。
入試傾向を分析すると、上記単元がよく出題されています。
設問レベルは標準レベルで基本的な問題が多いですが、選択問題・用語や文章記述・計算問題等、出題形式は多岐に渡ります。
入試過去問はもちろん、苦手単元に関しては過去の定期テストをやり直すのも有効な対策になります。
1つ1つ確実に覚えていきましょう。
2011年9月16日
福井県高校入試 理科①物理 傾向と対策
今回からは理科の傾向と対策をお届けします。
まずは物理です。
物理で最重要単元は「運動とエネルギー」です。過去問題を見てもほぼ毎年出題されています。
覚える内容が多く、計算も入ってくる単元ですが、まず1つ1つの用語・公式を確実に暗記しましょう。
記述式で解答を求められる問題も多いので、表面上の暗記だけではなく、
物体の運動・エネルギーの関係について仕組みまでしっかり覚えておく必要があります。
また、電流も頻出単元です。
こちらも覚える事が多いですが、電流が流れる仕組み、電圧の計算等押さえるポイントは決まっています。
1つ1つ確実に覚えていけば対処できます。
福井県の入試理科は、物理・化学・生物・地学の各分野からまんべんなく出題される傾向があります。
暗記ポイントは多岐に渡りますので、計画的に学習を進めて下さい。
次回は化学についてお届けします。
2011年9月15日
福井県高校入試 数学④確率の傾向と対策
福井県高校入試の傾向と対策。数学の第四回は、確率です。
「確率がわかりません」という声をよく聞きます。
何も難しく考える必要はありません。全パターンを数えれば答えは出ます!
たしかに時間はかかりますが、まずは数えてみる事で、数式で求める場合の式の意味が理解できる事も多くあります。
確率を苦手だと感じている人は諦めずに数える事、その上でそれを数式で表したら・・・と練習する事が大事です。
基本的な問題は解けるという方は入試過去問を利用して応用問題にチャレンジしてみましょう。
昨年は関数と確率の融合問題が出題されていました。
出題頻度は高い単元です。
確実に解けるよう練習して、志望校合格の確率を上げていきましょう!
2011年9月14日
福井県立高校入試 数学③平面・空間図形の傾向と対策
福井県立高校入試の傾向と対策シリーズ。今回は数学③平面・空間図形についてお届けします。
図形は空間図形よりも、平面図形の出題割合が高くなっています。
特に平面図形は、基本問題、図形の証明問題、面積に関する問題は過去3年間連続で出題されていますので、
今年度の入試でも注意が必要です。
また、昨年度は線分が垂直に交わることを証明する問題も出題されました。
きちんと証明もできるように、公式を確認し、証明の流れをきちんと把握しておきましょう。
2011年9月13日
福井県立高校入試 数学②関数の傾向と対策
福井県立高校入試の傾向と対策。今回は数学・関数についてお届けします。
関数は1次関数・2次関数ともに頻出単元です。基本的なグラフの書き方、式の求め方は確実に解けるように練習しておきましょう。
図形・方程式との融合問題がよく出題されるのも福井県入試の傾向です。
難易度は高めですが、上位校を目指す人は特に対策を取って下さい。
福井県の過去問や、他県の過去問などを使い、多くの問題にチャレンジしていきましょう。
関数は数学の分野の中でも特に出題頻度が高い単元です。しっかり復習して確実に点数に結びつけましょう。
2011年9月11日
福井県立高校入試 数学①計算・方程式・文章題の傾向と対策
新学期が始まり、いよいよ受験シーズンが近づいてきました。
中学3年生の皆さんは、とりあえず11月の学診で結果を出そうと頑張っている事かと思います。
今回から、福井県立高校の入試傾向を科目・単元に分け掲載していきます。今回は数学の計算・方程式・文章題についてです。
傾向をつかんだ受験勉強で、合格まで最短ルートで走り抜けましょう!
●数と式
正負の数の計算・1・2年で習った式の計算・平方根がほぼ毎年出題されています。
ここは落としたくない所ですね。簡単な計算ミスで失点しないよう普段から練習して下さい。
計算力は演習量に比例してついていきますよ。
●方程式・文章題
2次方程式・連立方程式共に頻出単元です。計算は確実に解けるようにしておいて下さい。
連立方程式の応用として文章題も毎年出題されます。多くの問題をこなし解法パターンを覚える事が正答への近道です。
また、連立方程式と1次関数の融合問題もよく出題されています。難易度は高いですが、上位高志望の方は特に対策が必要です。
以上になります。次回は数学・関数をお届けします。
2011年9月8日
福井県 土日の勉強は「例題」→「類題」
学生のみなさん、新学期の勉強は順調ですか?
すこし気を抜いていると授業はどんどん進んでいってしまいます。
定期試験においても、受験に向けても、まずはこまめな復習が大切です。
さて今回は土日の復習について紹介したいと思います。
土日は、1・2年生は部活の練習に追われ、3年生も模試や塾などに忙しいことでしょう。
しかし授業のない2日間を自分の復習の時間として大いに活用してほしいのです。
土日にまず最優先すべきは苦手科目の復習と定着のための勉強です。
苦手科目は人によって異なるとは思いますが、ここでは、特に時間のかかる理系科目の復習をお勧めします。
たとえば、土曜日には数学の例題を使って一週間の復習を行います。
そして日曜日には同じ分野のやや発展的な類題を使い、再度理解度を確認します。
もしも発展問題でつまづいた時はすぐに前日に行った例題で復習を行いましょう。
このように2日間にわたって同じ分野の問題を解くことで、より問題に対する理解を深めることができるはずです。
土日は1週間の整理を行うためにあるという認識のもと、週末を有意義に活用出来たらいいですね。
自分がどこにつまづいているのかを知るためにも、土日の復習を欠かさないようにしましょう。
2011年9月3日
福井県 勉強法の工夫「まず、やってみること」
8月が終わり、新学期がはじまりました。
夏休みを有効活用できた人も、計画倒れ等でうまく活用出来なかった人も、秋から心機一転頑張っていきましょう。
秋は運動会や合唱祭、校外学習など行事の多い時期です。
運動会の練習で忙しくて宿題をやっていない、体育祭の準備で疲れて授業に集中できない、といった生徒さんも見受けられるようになってきます。
行事を理由にせず、しっかりと勉強を続けられるように工夫しましょう。
授業が開始されたことで、夏休みに比べ自由に使える時間が格段に減少しています。
行事があれば、さらに時間が取れなくなってきますよね。
そんな中でも勉強を続けられるような工夫をしていかなくてはなりません。
勉強の仕方を変えるのは難しいことですし、「工夫しろと言われてもどうすればいいの?」と戸惑う人もいると思います。
しかし工夫の仕方や勉強のやり方が分からない、といって何もしないでいると、あっという間に秋が終わり、受験シーズンがやってきてしまいます。
まずは、「朝30分早く起きて勉強する」「授業が終わったらすぐにその授業を復習してから休み時間にする」
電車通学の人は、「電車内で寝ていた時間を暗記に充てる」など、思いつく簡単なことからやってみましょう。
それが続くか続かないか、自分に合うか合わないかはやってみないとわかりません。
自分に出来るか考える前に、まず、やってみましょう。
3年生は特に学診にむけて頑張っていきましょう。