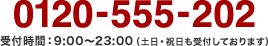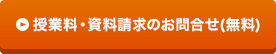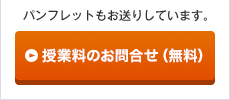2019年3月29日
2020年教育改革について
こんにちは!
間もなく3月が終わり、新年度に入ります。清々しく4月を迎えましょう。
2020年度より「大学入試センター試験」が廃止されることに伴い、
小学生・中学生の学習内容も変化します。
この変化は、子どもたちに求められる能力が変化しているからです。
従来の「知識の暗記」「情報処理能力」から、「判断力」「論理的思考力」「表現力」へと変化しています。
単純暗記ではなく、「与えられた知識をどのように活用するか」「自分の考えをどのように表現するか」が
問われており、学校で指導される内容も「知識の活用」が重視されていきます。
ポイント1:英語教育の変化。
日本の英語力は国際的に評価が高くありません。特に「話す」力においては、世界で最下位というデータもあります。
この状況を打破するため、小中高と一貫した指標で英語力の基準を決め、
小学校から英語を学ぶ環境を造ろうと文科省が動き始めました。
4技能を測定するためにも、英検をはじめ民間の「英語外部試験」が積極的に活用されていきます。
ポイント2:理系教育の変化。
科学技術や人口知能が発達するなか、2020年度から小学校でのプログラミング必修化や
中学校での統計に関する「データ分析」という単元を扱うなどの変化もあります。
ポイント3:大学入試改革の要点。
2021年1月にはセンター試験の後継となる「大学入試共通テスト」が始まります。
すでに高校生を対象に「サンプル問題」が実施されており、傾向が明らかになっています。
「暗記」ではなく、「知識の活用」に重きがおかれている点です。
新しい資料や情報が問題文で与えられ、既存の知識と結びつけて解答を導きだすというタイプの問題が多く、
解き方をひたすら覚える従来のパターン学習では太刀打ちできないことがわかります。
以上、3つのポイントを説明しました。これらの変化を頭の隅に入れながら、今後の学習に活かしてほしいと思います。
ではまた、次回にお会いしましょう。