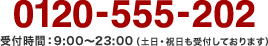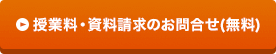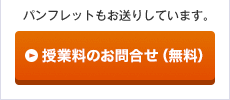2013年11月6日
群馬県 東京農大二高入試の傾向と対策 ~国語編~
東京農業大学第二高等学校(農二)の入試の傾向と対策についてお伝えします。
今回は『国語』です。
平成18年度からすべてマークシート形式です。
45分100点満点。
【大問1】(配点45点程度)
『論説文』※近年
親しみやすいテーマであり、自分の生活や身の回りの社会に照らし合わせて読み進めることを
目的としている。平成21年度のみ小説でした。
大問1の配点が100点満点中の45点前後を占めており、国語で点数をとる為に一番重要な大問
であると言えます。
平成21年度・・・『皮膚のない皇帝』 リンダ・セクソン(村上春樹訳)
平成22年度・・・『物理と神』 池内 了/キーワード:パラドックスの効用について
平成23年度・・・『思考の整理学』 外山 滋比古/キーワード:現代に生きる人の思考
平成24年度・・・『もののけの正体』原田 実/キーワード:もののけの存在と、江戸っ子の「いき」さ
≪出題内容・形式≫
・漢字で書いたときに、その漢字と同じ漢字を含むもの
・接続語
・指示後が示す内容(9~10問程度)
・語彙の意味
・熟語の対義語(4~5択から選択する)
・文脈の意味
・本文中の意味正誤
【大問2】(配点25点程度)
『古文』
著名な作品からの出典が多い。
古典文法や古典知識<本文中の内容理解
平成21年度・・・『十訓抄』 作者未詳/鎌倉時代中期の説話集
平成22年度・・・『古今著聞集』 橘成委/鎌倉時代中期の説話集
平成23年度・・・『宇治拾遺物語』作者未詳/鎌倉時代前期の説話集
『今昔物語集』と並ぶ、説話集の最高傑作
平成24年度・・・『十訓抄』 作者未詳/鎌倉時代中期の説話集
≪出題内容≫
・口語訳
・会話主や動作主
・行動の理由
・本文内容(8問程度。5択から選択する!)
・本文の主旨
【大問3】(配点20点程度)
『漢文』
例年漢詩の出題もあります。
基礎的な「書き下し文⇒現代語訳」「白文⇒書き下し文」(返り点のつけ方)や、
漢詩の形式、漢詩の特徴等をおさえておく必要があります。
古文と同じく、漢文文法や漢文知識<本文中の内容理解です。
平成21年度・・・漢詩
平成22年度・・・『韓非子』
平成23年度・・・『漱石詩集』 夏目漱石
平成24年度・・・漢詩
≪出題内容≫
・漢詩の形式(例:七言律詩、五言律詩、七言絶句、五言絶句)
・比喩、倒置法が使われている句(6~8問程度)
・読者に対する表現効果
・語彙の意味(5択から選択)
・白文に対する返り点をつける
・本文理由、解釈
【大問4】(配点10点)
国語の『知識に関する問題』
品詞や慣用句、ことわざなど、教科書、国語便覧レベルです。
平成21年度・・・文中の敬語用法、漢字の成り立ち(例:象形、指事、会意、形声文字)
熟語の構成、助詞の使い方、慣用句
平成22年度・・・会話文中の敬語用法、四字熟語、慣用句
平成23年度・・・ことわざ、文の繋がり(例:主語―述語、補語―述語)
平成24年度・・・ことわざ
≪出題内容≫
・敬語用法(例:尊敬、謙譲、丁寧)
・漢字の成り立ち
・助詞
・熟語
・文の繋がり(4~5択から選択)
・慣用句
・四字熟語
農大二校の国語対策!!~今から何する?~
【評論文】~筆者が読者に伝えたいことは何?筆者の主張を捉えよう!~
もう一度、教科書やすでに行ったワークなどの本文を読み返して、
☆指示語 ☆接続語 ☆表現の特徴 ☆本文中の一番重要な言葉、文
から、筆者の主張を読み取る練習をする。
上記☆に着目し、本文中に自分なりのマークをしながら読み進めてみよう。
【小説】~とにかく「変化」に気付く!本文を根拠に読み取ろう!~
もう一度、教科書やすでに行ったワークなどの本文を読み返して
登場人物に印をつけたり、情景が変わる瞬間に着目し、下記の『変化』に気づけるようにしましょう。
『登場人物の心情の変化』 『情景描写の変化』
表現の特徴・・・
比喩や、擬人法、繰り返し表現などを国語便覧等を用いて復習しておいて損はありません!
大問4にも繋がります!
【古文】【漢文】~どこまで知識の引き出しを増やせるかが勝負!~
1) 動作主、会話主を押さえる。(本文中に主語が書かれない場合があるのが、古文漢文です!)
2) 本文中の意味を訳し、解らない単語や文脈があったら、辞書や国語便覧を引き、
調べるクセをつけましょう。
3) 詩、漢詩、短歌、俳句などには特徴的な表現があります。それぞれの表現技法を確認しましょう。
(例:頻出!漢詩⇒押韻、対句、律詩・絶句の違いなど・・・)
【国語の知識に関する問題】~言葉は無限大。だからこそ、覚えた分だけ、点数に~
1) ことわざ、慣用句、四字熟語などは、辞書や国語便覧を見ながら、早いうちから
まとめる作業をしていきましょう。自分なりの語呂や、それらを使った文を作るなどして、
覚える姿勢を大切に!
2) 敬語や助詞などには様々な種類があります。日頃から、何が、どの敬語や助詞、はたまた
どんな品詞なのかを考え、具体的な文から覚えていくようにしましょう。