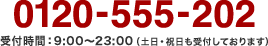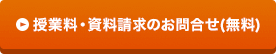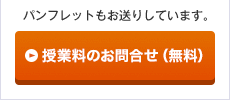2018年11月16日
定期テスト対策①
みなさんこんにちは。
今回は、定期テスト対策についてです!
ほとんどの学校で、11月末に2学期末テストが実施されるかと思います。
中学3年生の2学期までの成績が、受験する高校に提出されるため、
2学期の成績に大きく影響する今回の期末テストは、今まで以上に頑張って取り組みましょう。
では、具体的にどのようにテスト勉強を進めていくべきかのアドバイスを致します。
①全体を把握し、学習計画作成
期末テストは主要5科目に加え、実技科目も加わるため、必然的に勉強量も中間テストに比べ多くなります。
テスト範囲を確認し、学習計画をしっかりと立てましょう。
テスト範囲の決定が遅くても、大体の範囲は自分で予想を立てることができるはずです。
最低でも2週間前くらいを目安にテスト勉強を始めてください。
計画的に学習しないと、勉強する時間を確保できなかったり、
理解が不十分な状態でテストに臨まなくてはならない科目も出てくるでしょう。
必ずテスト勉強を始める前に、予定などを見据え、勉強時間をしっかり確保してください。
②迷ったら点数の上がりやすい科目から
「どの科目から、どの単元から手を付けていいかわからない」という生徒さまが多くいらっしゃいます。
そんな時は、点数の上がりやすい科目から手を付けてみましょう。
理科・社会や実技科目などの暗記がメインとなる科目などがおすすめです。
逆に、中間テストであまり結果が良くなかった科目や、自分の苦手とする科目から始めるのもいいと思います。
いろいろ工夫しながら、自分に合ったスタイルを確立していくことが大切です。
③繰り返しが定着へ
「時間が経つと忘れてしまうから」「一夜漬けが一番覚えれる」といった理由で、
テスト前日に一気に学習しようとしている生徒さまがいます。
まず、時間が経つと忘れてしまうのは当たり前のことで、忘れないように定着させるために勉強しています。
定着のために最も重要なことは演習です。
繰り返し問題を解くことで、知識は定着していきます。
勉強して、日をおいて改めて勉強する、この繰り返しが定着へと繋がります。
また、勉強していることを必要な情報として脳に記憶させる必要があります。
人は必要ないと認識した情報はすぐに忘れてしまうため、繰り返し問題に触れることで、必要な情報と認識させる必要があります。
一夜漬けで覚えられるという方に関しても、もし期末テストで点数が取れたとしても、今後使える知識にはなりません。
それは1度しか勉強していないため、定着しないからです。
定期テストで結果を出すことももちろん大切です。
しかし、今後の学習、そして受験まで見据えた勉強をすることがとても重要です。
④定期テストは教科書・ワーク
テスト勉強をする際に、教科書の問題・ワークを必ず解き直しましょう。
最低でも3回は解いておくと安心です。
学校の定期テストは先生が作成しているため、ワークの問題を少し変えたものであったり、
問題によってはそのまま出題したりすることが多々あります。
特に難しい問題などは、そのまま出すことも多いですね。
教科書やワークの問題は最低限解けるように、繰り返し解き直しておきましょう。
最初は教科書などで確認しながら解いても大丈夫ですが、
テスト前に必ず何も見ずに問題を解き、ちゃんと解ける確認しておきましょう。
上記を参考に、計画的にテスト勉強に取り組みましょう。
家庭教師のトライでは、生徒さま一人ひとりの状況、目標に合わせてオーダーメイドのカリキュラムを作成します。
「自分では計画的に学習できない」「どうやって勉強すればいいかわからない」
そういった方は、ぜひトライにご相談ください。
部活や習い事など、生徒さまによって環境は異なります。
それらを考慮し、山口県のトライさん(教育プランナー)が、
目標に向けてどのように勉強していけばよいか、学習計画の立案やアドバイスを行います。
そして、指導経験豊富な教師や、専門科目に特化した教師のわかりやすく丁寧な指導で、効率よく学習を進めることができます。
トライさんは、山口県の学校事情や受験情報にも精通しており、無料で学習相談や進路相談なども実施しております。
さらに、今月のキャンペーンとして、「成績保証コース」という定期テスト対策を目的としたコースをご用意しております。
ご興味のおありの方は、お気軽にお問い合わせください。
成績保証コースの詳細はこちら