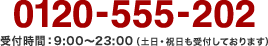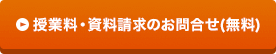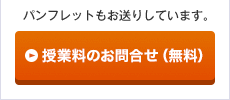2020年5月
2020年5月30日
6月になります。気を付けておきたいこと
月も明けて暦の上では夏となります。
6月は夏至といって年間でも日の出ている時間、すなわち日照時間が一番長い日もあります。
今年は6月21日(日)が夏至となりますがこれは1年間で最も日照時間の少ない冬至と比べて
およそ4時間も日照時間が長いという事になります。何気ない毎日の生活の中にも変化はあります。
きちんと対応してスケジュールを立てていきましょう。
よく「暗くならないと集中できない」という意見を聞きます。
確かに暗い空間での集中力の高まりはヒトに限らず多くの動物も持っている本能なんです。
そこから変化を加えていくのがポイントです。
同時に梅雨入りの時期にもあり、毎年受験生には健康管理に気を付けてもらっています。
それでも体調を崩されることもあります。そのポイントは以下の通りです。
①暑くなることで起こる体調の変化に注意
まず気温が高まるので体温を下げるためにエアコンをつけたり冷たいものを飲んだりという事をするようになります。
ここで気をつけたいのが「エアコンをつけたまま同じ姿勢で勉強することで肩や首に負担がかかりやすい」
という事です。夏になると肩コリや腰痛に悩まされる方はいませんか?
個人の体質にもよりますが、痛くなりやすいところは必要以上に冷やさないようにしましょう。
エアコンはつけているけど肩と腰はちゃんと温めておきましょう。
エアコンをかける時間を決めることや学習後にゆっくりお風呂につかり肩や腰を温める事も効果があります。
②1年間で最も寝坊が多くなるのが6月
梅雨入り前後の時期には私たちの体は気付かないうちにひじょうに強いストレスを感じているようです。
そのため、ついうっかり寝坊してしまった!という事はないでしょうか?
それ以外にもこの時期はお腹や頭が痛くなったという体調不良の中でもこういったストレスが要因になることも少なくありません。
また、この時期に体調を崩される方は真夏となる8月や寒くなる10月にも不安定になりがちです。
人間の体にある自律神経は季節の変化の際に疲れを感じやすくなっているため、という考えもあります。
体調なので仕方ない部分もありますが、特に受験生の場合は時間を無駄にはできません。
また智辯・近大付属などの私立中高一貫校については欠席がそのままテストの低下に直結してしまう例も見られます。
健康管理も成績アップのために非常に大事です。
この時期の体調キープの最大のコツは「夜更かししないこと」です。
逆に「まだ起きていられる気がする」といった過度な気持ちの高まりには要注意です。
体感的には夏至近くの時期には「暗くなってから〇時間」感覚も遅くなってしまいます。
生活スタイルはしっかり時計を見て過ごすようにしましょう。
各学校とも長かった休校期間も明け、徐々に本格的に授業がスタートしていきます。
定期テスト等の情報も少しずつですが入ってきています。どうやら学校の先生が指示する以上に復習はやっておかないと、
高い成績は保証できない状態ともいえます。
家庭教師のトライでは自習用にAIデジタル学習ツールとしてタブレットを配布しています。
その学習の反応がとてもよく、前の学年の復習や1学期内容の予習など一人ひとりの特性に応じた自習を行ってもらっています。
毎日を丁寧に送り、不安なことはいつでもトライに相談してください。
2020年5月26日
授業再開がもうすぐです!
5月も最終週になりました。
ほとんどの学校においては6月初頭から授業が再開となります。今週はその最終準備となります。
①通学用の生活スタイルに戻っていますか?
この休校期間を「長い春休み」と考えるならば、夏休みのように起床時間や就寝時間にズレが出がちです。
ましてや部活動も中止が多くなっていますので、気付かないうちに体力も落ちている事が多くなります。
毎日通学が再開してすぐは、非常に疲れやすい日々が続くと予想されますので、
今のうちに自律神経を安定させる対策、具体的には起床時間と就寝時間を一定にする・お風呂にゆっくり入るなど
日常生活をずらさずに送ることを心がけましょう。
②休校前より学習時間が減っていませんか?
休校期間中に強く意識付けて時間管理できていた人もいますが、生活リズムが大きく変わってしまった事で
学習時間が減ってしまった、という相談をよく受けます。
「学校が再開したらまたがんばろう」と思っていた皆さん、
休校前の学習はいつどこでどんなことをやっていたか詳細に思い出すことできますか?そしてその通りにできますか?
今回の休校期間でみなさんを最も苦しめてしまうのは実はこのポイントなのかもしれません。
再開まで残りわずか、しっかりとペースを取り戻しましょう。
トライで学習されている皆さんについては、配布されているタブレットを利用したAIデジタル学習活用が有効です。
午前中にデジタル学習を行うのかはかどりやすい、昼からもしっかり勉強しやすいなどといった意見をいただいています。
負担少なく、気持ちは前を向いて頑張っていきましょう。
2020年5月18日
いよいよ新学期がはじまる!今準備すべきこととは・・・!
5月も終盤になりました。
各高校や中学とも登校日を増やし、授業再開に向けて準備されています。
みなさんの準備はOKでしょうか?
学校再開後は早いペースで授業が進んでいくことが予想されます。
ついていけなくなった、ではお話になりません。きっちりと準備をして余計なストレスを溜め込まないようにしていきましょう。
部活をされている方は活動も再開になりますので余計な負担にならないように学習面の準備をしておくことが賢明です。
いかにポイントをまとめておきますので参考にしてください。
①まず授業時間集中できるか
授業再開が見込まれる6月は気候の変化点(気温と湿度の上昇・気圧の低下)でもありますので、
何もなくても集中力は低下しがちです。授業内の聞き漏れやノート漏れやヘタするとウトウトしてしまうこともあるかもしれません。
これはある程度予想できることなのですがしばらくの間は授業中にボーっとしてしまう方も多くなると思います。
当ブログを読んでくれているみなさんについては上記の点をしっかり意識したうえで、
「準備期間である今の時期に授業時間のあいだは休憩なく集中できるようにしておく」事を徹底しておきましょう。
実力テストや定期テストもそれほど準備期間を置かずに実施される予定です。
メンタル面の準備もしっかりしておきましょう。
②忘れてしまったこと対策!どこまで復習できるか
今回のように生活様式が変わってしまうと学習習慣も変化しがちになります。
特に「前の学年内容の復習」は「やったつもりがうまくできない」などよく耳にします。
中学生以上になると「ひとつの事柄を理解できていないと、次の単元が全くわからない」事がよくあります。
数学でいうと正比例を理解できていないと一次関数がわからなくなり、二次関数は全くとけなくなりがちです。
同様に英語だと三単現→過去形→完了形や受け身(過去分詞)などこういった現象は無数に存在します。
過去の復習が大事になってくるのはわかります。
ではこの過去の復習はさほど難しいものではなく、めんどくさいのが難点です。なるべく負担少なく復習したいものです。
トライでは今春より「AIデジタル学習」を導入しているのですが、個人の進度やレベルに合わせて過去に履修を完了した分野であってもタブレット上でいつでも復習できるようになっています。
トライですでに学習している方たちにはこのステイホーム期間に、おおよそ1年分の復習を完了された方も多く、新学期の点数の伸びに期待できるところまできております。
興味のある方はいちど問い合わせてみてください!
2020年5月11日
学校授業再開に向けて
5月も2週目になります。
自宅待機期間が終了すればいよいよ1学期が始まります。
学習スタイルや到達点がズレてしまうこともよくあります。
新学期が始まる前にチェックしておきたいことを挙げておきますので参考にしてください。
①授業時間中集中できるか
学校ごとで授業時間は違いますが、まずご自身の学校の授業時間のあいだは集中できるようにしておきましょう。
この期間に机につくけどすぐ飽きてやめてしまうクセのついてしまった方は要注意です。
②自主学習と大きくちがうのは「何度も見直せない事」
自己学習と大きく違うのは「先生が目の前で教える」ことにあります。
確かにメリットも多いですが、一度言った言葉はメモを取っておかないと、なかなか繰り返してくれないといったデメリットもあります。
先生の言葉や板書をすばやく自身のノートに写すといった作業はこの数か月やっていない方も多いと思います。
しっかり意識付けておきましょう。しばらくの間は復習ノート、といっても学校ノートを清書するだけでもやったほうがいいでしょう。
③学習の中で最も大事なこととは
トライで学習している方ならご存じな方も多いですがトライでは学習の内容を「習得・習熟」と「演習」に分けています。
「習得・習熟」・・・参考書内容や先生の説明を理解して頭に入れること
「演習」・・・得た知識をもとに実際に自分で問題を解き、正解まで導くこと
つまりは長時間勉強していても、問題で正解が取れなければ効果もなかったことになります。
ここで重要なのが、今のご自身の勉強方法でテストの問題でキッチリ正解が取れるのかということです。
今一度考えてみましょう。
トライの家庭教師で指導を受けている皆さんは、講師やトライさんに相談してみてください。
一人ひとりに合わせて最善のアドバイスができます!
2020年5月9日
休校期間中の学習のコツ
5月にも入り、ゴールデンウィーク期間も終わりました。
ただ、今年についてはご存じの通り新型肺炎の流行拡大により各中学校・高校とも休校となっており、
これまでにない生活を送っておられると思います。
休校終了のお知らせもあまり入っていないようで、皆さんの不安も計り知れないのではないでしょうか?
「学習面に遅れが出るかもしれない」
「再開した授業は厳しいに違いない」
といった学習面の不安もあるでしょうが、それだけではないと思います。
友人や部活の仲間と会えないストレスも相当あると思います。
だからといって無理やり外出することもできません。
今しばらくは自宅でじっくり待機しましょう。
さて、3月以降自宅での学習を行っている皆さんの中で「飽きた」「集中できない」といった悩みをお持ちの方は
いないでしょうか?
今回はこの「飽き」について少し説明していきます。
「飽き」には2種類あることを理解しておきましょう。
よく「飽きた」という言葉に集約されますが厳密には飽きというのは2種類存在します。それらの特徴をわかっていれば
対処法も楽になります。
a.「同じ作業を何時間も続けてやっている時」
b.「同じ習慣を何日も続けている時」
の2種類なのですが、飽きるというのはいずれも脳が疲れを感じている状態ですので、飽きを感じているが無理やり続ける
事は必ずしもよい行動とは言えないようです。効率も落ち、疲れも回復しにくくなります。大事なのは適度な休憩など
対処法を知ることです。
a.「同じ作業を何時間も続けて飽きてしまった」
・・・継続されている時間にもよりますが、飽きよりも疲れと判断したほうがよさそうです。
ここで必要なのはリラックス作業です。いわゆる軽い運動や音楽鑑賞などが言えるのですが、
この中でも運動を強くおススメします。学習後の運動は脳細胞を増加させ、記憶機能を活性化するはたらきがあります。
特に有酸素運動といわれる多くの酸素を必要とする運動が良いとされます。
このことは大学の論文でもしばしば論じられることもあり、
「学習した4時間後の有酸素運動が最も記憶機能が増大する」
「メンタル面での不安も軽減される」などの報告も上がっています。
ここでいう有酸素運動とは屋外だとウォーキングやジョギング、屋内だとダンスや体操などが当てはまります。
ぜひ試してみてください。
b.「同じ習慣を何日も続けて飽きてしまった」
・・・a.と違うのは「短時間でも飽きてしまう」点です。これはわかりやすく言えば新鮮さがなくなったと考えればいいと思います。初めて当初は目新しい方法や問題集や教材に気持ちもノリノリだったのですが、いつしかその刺激もなくなり 始めるのが億劫になっていく・・・といったものですが、当然ながらこれらは良い傾向ではありません。
ここでの対処方法としては「やり方を変えてみる」事に他なりません。
相手が問題集なら音読しながら解くなど、「口に出してみる」ことが有効です。または科目・分野を変えずに問題集だけ変えてみてもいいかもしれません。ここで大事なのが脳が新鮮さを感じるかといったことです。脳というのは不思議な器官でしばらくほかのことをやり続けて、それにも飽きてきたころに元に戻すとまた新鮮さを感じるようです。
皆さんも「聞き飽きたはずの音楽を久しぶりに聞いたら新鮮さがあった」や「飽きたはずのゲームを久しぶりにやったらなぜかはまった」という経験はないでしょうか?それと同じ現象です。ここは工夫し甲斐はあると思います。
トライの家庭教師で指導を受けている皆さんは、講師やトライさんに相談してみてください。
一人ひとりに合わせてきっといいアドバイスができると思います。